抒情文芸 第196号
短歌が入選、俳句が佳作でした。
作品の投稿とは別に読者のお便りコーナーみたいなやつがあるんだけれど、その中に、若い人は若い人たちだけでネットでやってて雑誌に投稿する楽しみは過去のもの、みたいなことを書いている人がいて、そんな認識ボンクラにも程があると思いました。本屋に行ってるのか。雑誌見てるのか。投稿サイト見たことあんのか。メディアによって優劣あるとか思ってんのか。「私達だけは」とか言って主語広げんな、一緒くたにすんな。
ネットが母体の若い人たち、みんな勉強してるよな。時流というのはあるにせよ、それでも上手い人は上手いし、いい作品はたくさんある。若い人は、学校通ったり仕事したりしながら貪欲に色んなこと吸収して、凹んだりもしながら書いて書いて。そりゃあ、くっだらねーなと思うものも山ほどあるけどそんなのどのメディアだってどの年齢だってそうじゃねーか。抒情文芸の読者層は子供どころか孫も成人してそうな年齢なのかも知れんが、今の若い人たちは、なんて言ってる暇あったら読んで書け、百万遍でも読んで書け、この世にあるもの全部読め、そんで書け、くらいに思いました。自分に向き合うこと、時流を見ること、それは線を引いて区分けするようなことじゃないはずだ。
件の投稿は先号の選評に米川千嘉子先生が書かれていたことに呼応してのことなのかなとも思うんだけど、あなたはあなたで自信を持ってお詠みください、というのは、ネットでやってる人たちと雑誌投稿は別物でいい、ということではないんじゃないのか。表現方法や着眼点は別だとしても、詩なり文章なりを書こうとする行為や姿勢がそこにあるわけでしょう。
この夏、カクヨムの企画に参加してみて自分は凄く新鮮だったんだ、自主企画で出てくるお題とか公式の短歌塾でのテーマとか。これまで考えることがなかったものがどんどん出てきて、その都度七転八倒しながら書いて。反応はあったりなかったり、ないならないで考えたりもしたけど、詰まるところ自分は自分だってところに行きつくわけですよ、受けを狙って受けたところでなんにもならんのだもの。
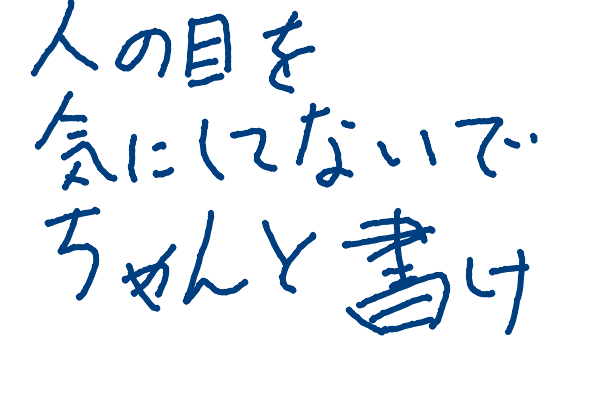
年寄りには年寄りにしかない経験や物の見方がある、若い人には若い人にしかない感覚や熱量がある、それは敵対するようなものではないよね。創作の評価軸が年齢やメディアだなんて、そんなバカな話があるか。
と、そんなようなことを考えて憤慨じみたことになっておりました。フンガー。イベント一週間前だというのに。フンガーフンガー。
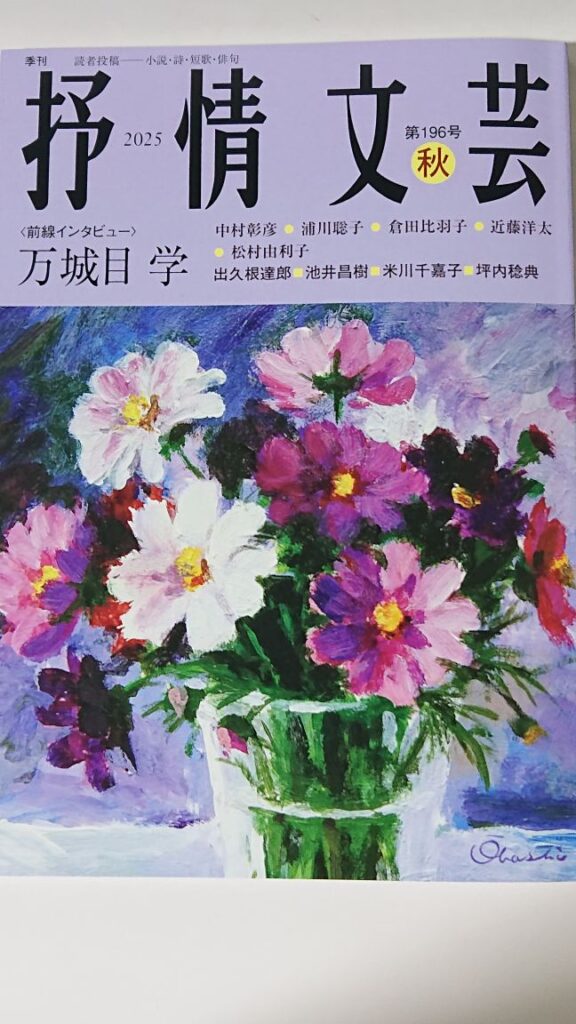
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません